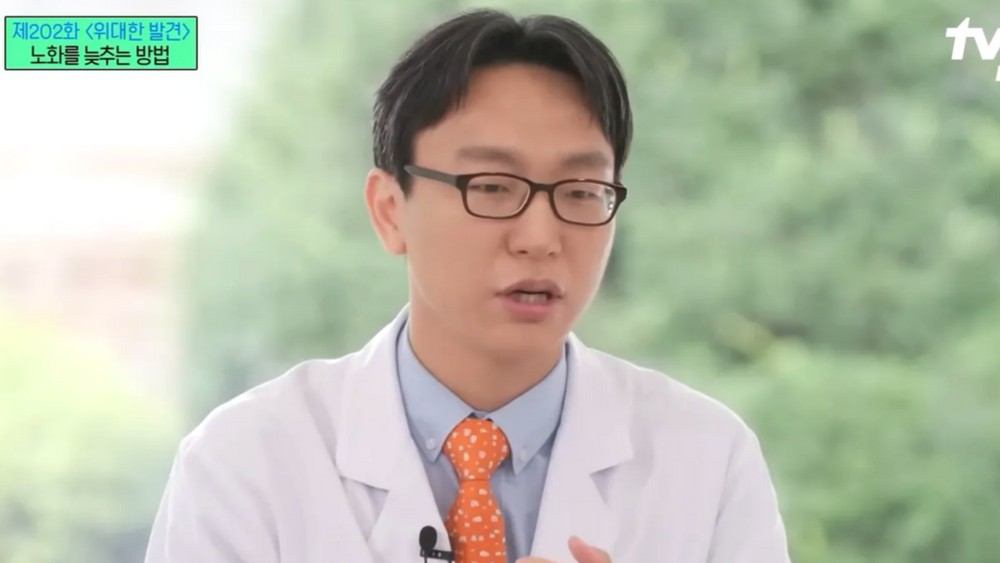アントニオ猪木のスパーリングパートナー・木村健悟
格闘技史の金字塔“アリ戦”での特訓相手にも指名され、猪木の技の進化を間近で受け止めた男がいる。木村健悟だ。
昭和の新日本道場で、猪木から「プロレスは闘いである。師匠と思うな、倒しに来い」と叩き込まれ、藤波とのライバル心を燃料に強さを求め続けた。猪木がいるだけで空気が変わる、あの緊張感の中で育まれた“闘魂”は、引退後も彼の背中を押し続けている──。
猪木イズムを求道し続けた男達が語る、新日本道場の最強伝説を集めた著書『アントニオ猪木と新日本「道場」最強伝説』(宝島社)より一部を抜粋して再構成。【全3回の第3回】
猪木のスパーリングパートナーに指名
昭和・新日本道場の代名詞のように語られるのが寝技のスパーリングだ。藤原喜明、佐山聡、前田日明といった、のちに第一次UWFに参加する選手たちのインタビューでたびたび語られてきたが、「プロレスは闘いである」という猪木の教えの根幹ともいえるスパーリングを木村はどう見ていたのだろうか。
「印象に残っているのは、やっぱり猪木さん、坂口さんとするスパーリング。ひと味もふた味も違っていた。猪木さんとスパーリングすると、ずば抜けた力はないんですが、技のツボを押さえていて、柔らかさがあって、技のバリエーションも豊富で、すぐに極められてタップをしていました。
坂口さんは全日本柔道選手権で優勝(1965年)して日本一になっているだけあって、体に一本の線というか芯があって、体幹がとても強かった。柔道仕込みの寝技はお手のもので、それでいて身長があって重いから、押さえ込まれたら終わり。猪木さん同様、すぐに極められてギブアップしていました。
そして私にとっていちばん忘れられないのが、永遠のライバル、藤波さんとのスパーリング。当時は『この男を引きずり降ろさないと上には行けない』と思っていたので、スパーリングも試合とまったく同じ気持ちでやっていました。自分の記憶では藤波さんに極められたことはないですが、極めたこともなくて、勝負は五分だったと思います」
これまでの昭和・新日本道場の取材は、いわゆる「ゴッチ教室」や「藤原教室」で切磋琢磨したU系の選手たちのインタビューが中心だった。しかし、それらの選手とは系譜が違うとされている木村が、猪木のスパーリングパートナーに指名されたことがあった。1976年6月26日、日本武道館で行われた猪木vsアリ戦における猪木の特訓相手を務めたのだ。
「あの時のことは今でも鮮明に記憶に残っています。アリとの格闘技世界一決定戦に向けた特訓で、私がアリに体格が似ているということでスパーリングパートナーを務めたんです。
あのアリが帰国後に病院送りとなったアリキックは、私が練習で受けていました。猪木さんのローキックは、寝た状態からでもすごい威力だった。あくまで練習なので私は足にサポーターをつけていたんですが、その上からでも効いた。練習後、足に相当なダメージが残ったのを覚えています。それで、『この蹴りなら猪木さんはアリを倒せる』と、一人でニンマリしていましたね(笑)。
あと、特訓中は低い体制からのハイキックの練習もしていました。これはあとになってわかったんですが、このハイキックこそ、のちに猪木さんの代名詞であり必殺技になる延髄斬りのベースになった技だったんです。そう考えると、価値ある時間を過ごさせてもらったと感謝しています。足は痛かったですが(笑)」

残した名言も多いアントニオ猪木さん(写真=東京スポーツ/AFLO)
道場での忘れられない猪木の言葉
木村が新日本で現役生活を過ごした1973年から2003年まで、新日本道場の練習メニューが大きく変わることはなかった。しかし、道場に猪木がいるのといないのでは、雰囲気は大きく異なり、緊張感がまったく違ったという。
「私が新日本にいた間、道場の練習メニューはほぼ同じだったと思います。だからこそ、猪木さんの存在の大きさを痛感しました。猪木さんが道場にいるだけで、そのオーラが選手たちの体を押して、限界を超えるまで動けるような感覚になるんです。それが“闘魂”なんですかね。
私にとって猪木さんは、闘う人間のピラミットの頂点でした。それを新日本のみんなが下から支えている感覚。プロレスの奥深さを教えてくれたのも猪木さんでした。様々な局面での対応や、相手の力を利用する、うまく吸収する懐の深さ、柔らかさなど、猪木さんの真似をしたくても、永遠にたどりつけない世界なんだということを痛感しました。
道場の練習で猪木さんは、『プロレスは闘いである。師匠と思うな。闘う相手なんだから、遠慮しないで倒しに来い』と常に言っていました。また、昭和の時代、プロレスを好奇の目で見る人は多く、『世間にプロレスを認知させたい』『プロレスラーは強くてすごいんだ』『キング・オブ・スポーツなんだ』という思いを、身を捧げて実践していたと思います。
そんな猪木さんの教えを受けていた私たちですから、全日本プロレスとしのぎを削る関係だった当時、道場で切磋琢磨していた仲間たちは、全員が猪木さん、新日本の屋台骨を支えているんだと自負していたと思います。だから『もし全日本と闘うことがあれば、いつでもやってやるぞ!』という気構えをみんなが持っていたんです」
2003年に木村は現役を引退。その後の約3年間、新日本のスカウト部長とプロレス中継番組『ワールドプロレスリング』の解説を務めた。現役を退いたばかりで右も左もわからないなか、 木村は「とにかく新日本をよくしたい」という一心で頑張った。たとえその場に猪木、坂口、小鉄がいなくても、与えられたことは一生懸命やるという精神は、新日本道場で培ったものだと木村は自負する。
「猪木さんのようにプロレスファン以外でも名前を知っていて、今でも話題になるような偉大な選手はそうそういないですよね。だからこそ今のプロレスラーにも猪木さんの栄光の過去を学んでほしい。先人が築いたプロレスの歴史を知ってほしい。昔と今のプロレスは違うって頭から否定しないでほしい。猪木さんほどプロレスのことを考え抜いて、それをリングで実践してきた選手はいないんですから。
早いもので、猪木さんが亡くなってから3年ですか。今でも不意に猪木さんのことを思い出すことがありますが、これほどプロレスを愛していた人は他にいないと思います。私は今、猪木さんもかつて身を置いた政治の世界にいますが、師匠・アントニオ猪木の教え、猪木イズムは私の中で生き続けています。それは、プロレスラーとして名声を得て、プロレスを通じて人の役に立ちたい、世間のみなさんに恩返しをしたいということに尽きます。
猪木さんには遠く及ばないかもしれませんが、これからも一歩でも半歩でも近づく努力をしていきます。昭和の時代の新日本道場での厳しい練習を思い出せば、どんな困難が立ち塞がっても、少しでも前に進めると思うんです。本当にありがとうございました」
取材・文/藤木健太
(了。第1回から読む)

1990年2月10日、東京ドームで坂口征二と組んで橋本真也&蝶野正洋戦に臨む試合前、控え室で「もし負けたら」と問うレポーターにいきなりビンタをかまして一言。試合後に初めて「1、2、3、ダー!」が披露されたことでも知られる

1985年9月19日、藤波辰巳(現・辰爾)との師弟対決にて。足4の字固めを耐えながら、「俺の足を折る覚悟があるか」と愛弟子に迫った。試合は卍固めで猪木が勝利したが、両者はこの3年後再びまみえ、伝説の60分フルタイムドローを闘い抜いた

1974年3月19日、「昭和の巌流島決戦」と謳われたストロング小林との対戦をジャーマンスープレックスホールドで制した試合後の言葉。“過激なプロレス”と称されるきっかけとなった